ごとう祐一オフィシャル > これまでの取り組み
政策提案
カテゴリ
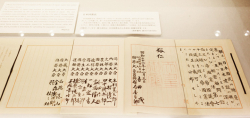
憲法についての考え方

城山ダムは事前放流できた
2018年7月の西日本豪雨災害を受け、国土交通省は2018年12月、台風豪雨が来る前日までに大胆に水位を落としておく「事前放流」を行うための「事前放流実施要領」を作るよう全国のダムに呼びかけました。しかし、作ったのは国が所管するダムと、三重県以西の県営ダムのみで、東日本の県営ダムは一つも作っていないことを11月27日の国土交通委員会で明らかにしました。
台風19号の豪雨で、実施要領を策定していた宮ヶ瀬ダム(国土交通省管理)は事前放流を行い、緊急放流せずにすみましたが、城山ダム(神奈川県管理)は事前放流を行っておらず、結果として人命のリスクのある緊急放流を行うことになってしまいました。11月20日に行ったダム管理所長へのヒアリングで、前日までにあと8m水位を落としておくことが可能だったことが明らかになっています。
今年の台風シーズン前に、国土交通省及び城山ダムを管理する神奈川県にも働きかけ、城山ダムをはじめ全てのダムで「事前放流」を可能とするよう徹底させてまいります。(2020.01筆耕)

韮尾根盛り土計画阻止(盛り土規制法案を提案)
2024年7月19日、盛り土計画を提出していた事業者がついに事業廃止の届出を相模原市に提出。計画阻止が実現しました。(2024年9月25日筆耕)

地球温暖化についての考え方


科学的な廃プラ政策を

非科学的な姿勢
ダイヤモンドプリンセスが横浜港に向かっていた2020年2月4日の予算委員会で「乗客に自室から出ないよう指示すべきでは」と質問。加藤厚労大臣は「他国の船だからできない」。翌5日に自室外への外出禁止となったが時既に遅く、712人の大量感染となった。
中国は1月末に断定していた「発症してない感染者からの感染」の可能性を、私が1月28日の予算委員会で加藤厚労大臣に聞くと「確認されていない」、2月4日に再度聞くと「分からない」。6月15日になっても「まだ評価が定まっていない」。発症していない感染者からも感染するので、どこでうつるか分からないことこそ、インフルエンザと異なる新型コロナの最大の特徴なのはもはや常識。一旦認めなかったことは意地でも認めない。専門家会議の議事録も作成しない。非科学的な政府こそ危険です。(2020.07筆耕))

公文書改ざん防止法案を提案
「安倍昭恵総理夫人」といった公文書の記述を決裁後に改ざん(削除)していたことが明らかに。改ざんは罰則の対象とする「公文書改ざん防止法案」をとりまとめ、2018年5月17日、野党各党で提出しました。予算委員会で私の名前を挙げて紹介されました。(2018.06筆耕)

公文書管理法改正案を四度提出
森友・加計・桜を見る会問題などは、公文書の隠蔽、改ざん問題に行き着きます。根本解決するための公文書管理法の改正案を4度提出、情報公開法改正案も提出しています。(2021.09筆耕)







